【助成事業紹介】岩室AIRプロジェクトPRE2024(新プロジェクトへのチャレンジ助成)
- その他
- 地域文化拠点
- 演劇
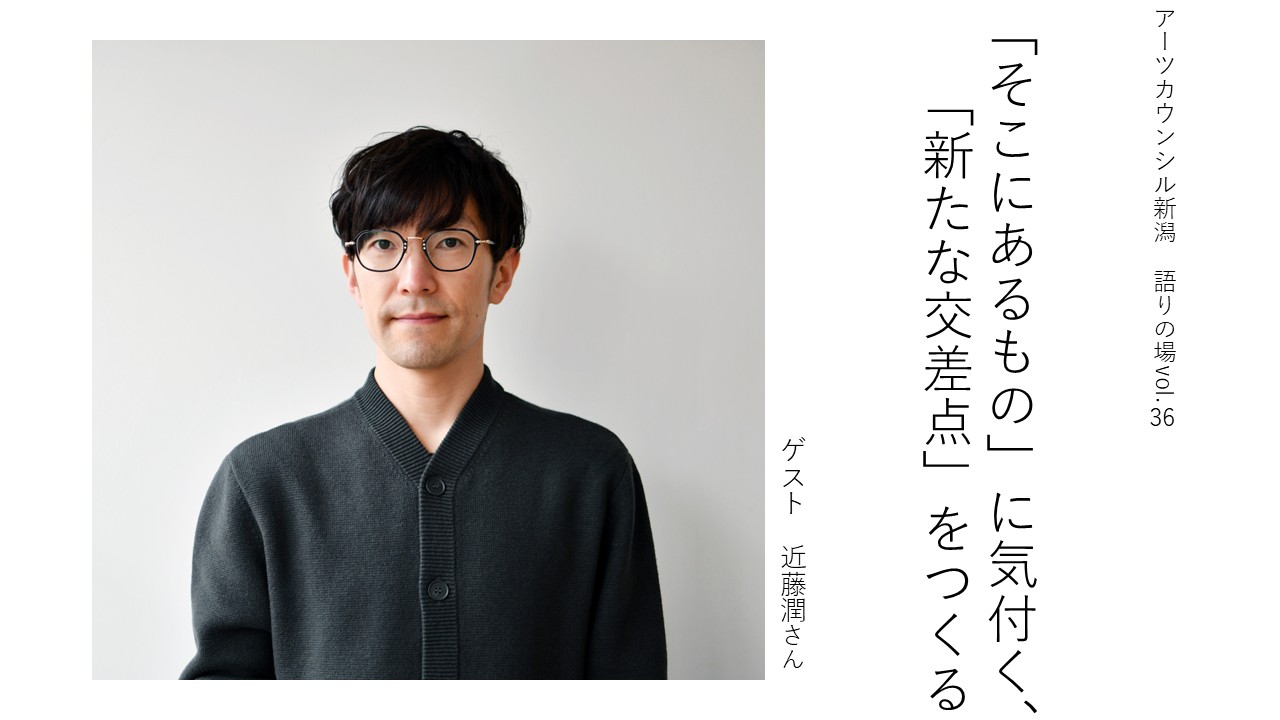
――近藤さんの過去から今に至るまで、という流れでお話を伺ってまいります。
まずは、近藤さんのプロフィールが、「ロンドンの建築設計事務所に勤務後、2015年に地元新潟市で独立」から始まっていますが、建築家になろうと思われたきっかけをお聞かせください。
出身が新潟市中央区の女池地区なのですが、自分が小学生の頃に実家を増築したことがあって、それを幼心におもしろそうだなと見ていたのがきっかけで、大工さんか建築設計の道に行きたいな、とおぼろげに思っていました。そして、高校卒業後すぐに東京の大学に行きました。進路選択にあたり、大工以外に設計というものがある、大工ではない別の関わり方もあることを知ったということと、大学の建築学部に行ったら大体みんな現場作業というよりも設計士、裏方で図面を描いたりすることがメインで、自然とそっちに行ったという感じです。
――建築士の資格を得るには実務経験も必要になるそうですが、近藤さんは、東京の大学卒業後にロンドンの建築事務所で実務経験を積まれています。なぜロンドンに行こうと考えられたのでしょうか。
ではここからはプロフィールの紹介もしていきますね。
今、軸が2つあって、アートディレクション含めプロダクトデザインやグラフィックデザインなどブランディング含めたデザイン全般と、設計です。関係した例として、クロスパルにいがたの近くにあるatoriさんというお弁当屋・お惣菜屋さんの設計プロジェクトがありました。これは、お店のデザインだけではなく、お店の雰囲気をどうしようかとか、場所をどうしようかといったブランディングも含めて一緒にやらせてもらいました。atoriさんは、後で重要なキーワードになってきます。
バックグラウンドとしては、建築の大学に進み、あまり表に出したことはないのですが、学部3年生の時に、保育園と老人ホームをくっつけるプロジェクトを設計しました。この頃から、まちと建築のつながりにすごく興味がありました。普通に建築学部建築科の学生をやっていたのですが、自分は模型を作るのが得意で先輩の手伝いによく呼ばれていました。その中で、海外におもしろい大学がある、建築専門の大学がある、そこにピーター・クックという人がいると聞きました。ピーター・クックは、普段設計事務所に通いつつ、 アーキグラムという集団で、「ウォーキング・シティ」をはじめとして、こんなものができたらおもしろいよねというものを掲載した今でいうZINEみたいなものを作り、世界中に送ってたんです。そこに載っているものはずっと実現せず、30年ぐらいただ妄想を続けている人達でした。そんなことをずっと考えてる人たちが教えている学校 Architectural Association School of Architecture に最初に興味を持ちました。それでロンドンに留学したいとなりましたが、自分が行くタイミングでピーター・クックがロンドン大学の建築学科に移ったので、先輩が教えてくれた大学ではなくて、自分はピーター・クックを追いかけて、そちらの大学に行きました。
――ロンドンではどのような勉強をされていたのですか。
実はロンドンでは2つの大学に行きました。最初に行っていたのはピーター・クックが教えている学校で、いわゆる建築の設計ではなく、ユニットごとに映像を作ったり3Dプリンターで不思議な造形を作ったりするような、すごくキャラクターがあって芸術学部に近い感じなんです。日本と全く違う教え方で、図面を描くのではなく絵を描くのに近く、いろんな表現を追求している感じなんですよね。それで自分も例にもれず、全く建築とは関係ない方法で建築を考えることをやっていました。ちょうどこの時にプログラミングに興味を持ち始めて、プログラミングに特化した建築をやっていたウェストミンスター大学に移りました。日本の大学に通っていた時に、ライゾマティクスの齋藤 精一さんがコロンビア大学から自分と同じ大学に帰ってきて、その方が3Dをどんどん使って映像を作ったりしていて、学生に教えてくれていたんです。なので日本にいた時から興味は持っていて、ロンドンに行っていろいろとつながり、自分もそういうのをやってみたいなと思って大学を変えました。
日本の大学と違うのは、1年を通してずっと同じプロジェクトをやり続けます。ウェストミンスター大学では最終的に、水をスクリーンにして映像を投影するというプロジェクトをやりました。映像なので見えているのですが、スクリーンにしている水を止めた瞬間に映像が消えます。映像を見ている時は没入感で映像の中に入り込んでいる感覚になるけれど、スクリーンがなくなった瞬間に映像もなくなり、はて今自分はどこにいるんだろうという不思議な感覚になるというものです。人が近づくと水が止まる仕組みになっているので、よく見ようとして近づいたら映像がなくなる、という不思議な体験を研究していました。インタラクティブデザインと呼ばれるジャンルですね。
――どちらかといえば、デザインや美術的な研究をロンドンの大学でされて、その後ロンドンの設計事務所に就職されるんですよね。
こういうことを大学でやっていたので、インタラクティブデザインをやっているところに就職したくて、いろんなところに作品集を送っていたんです。その中で唯一、来ていいよと言われた所がありました。そこは、3ヶ月インターンしたらみんな独立していくからということで、ほとんど個人でやっている作家さんばっかりの所でした。それだとビザが取れないので諦め、普通の建築事務所に就職しました。
そこでは、ロンドンのハムステッドという高級住宅街の個人宅やマスタープランの設計をしたりしていました。マスタープラン、今でいう再開発ですね。再開発と言うと、全く新しいものを作る感じですが、すごく高い7階建ての建物がボンボン立っていたものを2階建てくらいの住宅に変えてどのようにまちになじませるか、というまちなみをつくるプロジェクトもしていました。
――大学3年生の時に道に接続する建物の設計を考えられたお話と、ロンドンでのお仕事の話をお伺いして、まちの中にどのように建物があるのかを大事にされてるのかなと思いました。どのようなことをロンドン時代のモットーにされていましたか。
日本の時からあまり自分の意識は変わってなくて。ただ、イギリスは本当に「まちの文脈」をとにかく重要視している。100年以上前から変わらないまちなみの中に新しい建物を作る時、普通は周りの反対にあったりするじゃないですか。その人たちを説得するために建築家は本みたいな資料を作ります。日本でいう確認申請という建築許可をとる際に、なんでこの建物はこの場所にあって、どういう素材を使っているのかというのを1冊の本にして説明するんですよ。それを作るには、周りのリサーチから始めて、どういう素材を使っているまちなのか、といったことまで全部書くので、おのずと「まちの中にある建物」という文脈でしか設計できない。むしろそれがおもしろさになっていきました。
実は、ロンドンでは建築以外のこともやっていました。三味線を弾くブラジル人ミュージシャンの友達から依頼され、イベントのフライヤーを作ったこともあります。フライヤーデザインは、いろんな人が一晩一か所に集まって演奏してまた別々の道に行くというイベント(「G.A.T.E a Gathering of Affinities. Time and Ethnicities」)のコンセプトを反映して、アンティークマーケットで買ってきた時計を分解して門に再構成したものを写真に撮ってフライヤーにしました。動いていた時計を止めてその一瞬、その一晩を表現して、そして門をくぐってそれぞれ道に行く、といったことを表現しました。
――建築設計だけではなくデザインなどにも取り組まれていましたが、2015年には日本に戻って来られます。なぜ日本に、しかも新潟に戻ってこようと思ったのですか。
30歳のタイミングで次ビザを更新したら永住権が取れる状態だったのですが、そのままイギリスにいたいのか、いつか日本に帰るのか、この時に決めた方がいいな、と思ったんですね。永住権をとるということはずっといるということだし、いずれ帰ろうと思っているなら永住権をとっても意味がないなと思って、日本に帰ることに決めました。
決めるきっかけも本当にたくさんあって、東日本大震災で日本のことを考える時間が多かったり、ロンドンで追悼イベントを自分で開催していたこともありました。また、ちょうどその頃、日経新聞のオンラインで、高知を拠点にされているグラフィックデザイナーの梅原真さんが地域でいろんな活動をして盛り上がっているという記事を読みました。東京や大阪じゃないローカルで、しかもグラフィックデザイナーがいろんな活動をされている雰囲気から、ローカルの動きがすごくおもしろいなと思いました。それもあり、新潟でやるのもおもしろいかな、と思ったんですよね。実家も出身も新潟というのが一番大きいですね。
――ここからは、新潟での近藤さんの活動について伺っていきます。 2015年に戻って来られて、新潟の印象はどうでしたか。
めちゃくちゃおもしろいまちだな、と感じましたね。18歳で新潟を出ているので、全然地域のことを知らなかったなと思って。それこそ地元の小学校のあたりのことしか知らなくて、でも中学くらいから古町の方にはよく買い物に来ていたので、まちのおもしろさは知っているつもりだったのですが、18歳ではまだ飲み歩けないじゃないですか。夜の鍋茶屋通りへ初めて行った時に「こんな場所あるんだ」と思って、「すごくおもしろいな、新潟って」と徐々に気付き始めた感じですね。
2016年のNIIGATAオフィス・アート・ストリートでは、一筆書きで上古町から下本町まで掃除機で砂を吸って創作した作品を出品しました。まちを掃除機で吸って歩いている時に、何をやっているんですか、と何人か話しかけてきてくれましたが、全然誰も突っ込んでこないんですよ。横断歩道を渡っても全員無関心で通り過ぎて行くんですよね。そんな感じで一番町から十三番町まで一筆書きで1日で砂を採取していきました。サンプリングしたものを最終的に一番町から順番に積層させて「まちのちそう」という作品にしました。これの作品は、砂を通して見たまちの地図ですよね。白山神社のあたりは展示ブロックが剥げて黄色い砂が多かったり、柾谷小路あたりはアスファルトとか車の排気ガスが多くて黒っぽかったり、下(しも)の方に行くと白っぽくなりました。
――なぜ砂を採集しようと思ったのですか。
新潟に興味を持ち始めた時にまち歩きによく参加していて、その時に、新潟は砂のまちで、砂に翻弄された歴史があるということを聞いていました。また、祖父からは、昔は砂浜が300mくらいあって裸足で行くとやけどしそうになるという話を聞いていました。でも今は砂浜があまりないですよね。その砂がどこにいったんだろう、というのがきっかけで、まちの中から記録してみよう、みたいな感じですね。
――ロンドン時代はもちろん新潟に帰ってきてからも、アートに関する活動もされていますよね。建築とそれ以外という分け方をしてお話を聞いていましたが、実際はすごく親和性のある分野という気がしています。アート的な活動をすることで近藤さんの建築家としてのお仕事にどのような影響があったのか、逆に建築家だからこそアート的な活動にこんな影響があった、ということはありますか。
私は、境目がない、アウトプットが違うだけだと思っています。基本的に考え始めは、まちのプロジェクトであればまちのことを考えて、郷土資料とかをすごく読み漁るんですよ。2016NIIGATAオフィス・アート・ストリートでは、「みなとまち新潟~未来につなぐ歴史・文化のまち~」というテーマが決まっていたので、その中で砂を使って表現するとしたらどんなかなと考え、「まちのちそう」が出てきました。建築の設計はアウトプットとして建物というフォーマットになっているだけで、出口が違うだけで全く入口は一緒という感覚があります。考えるプロセスは常に同じですね。
デザインや建築の仕事はクライアントがいて依頼があるので、それに対する答えとしてやりますし、アート活動に関してはその制限がないので、自分の中ではもっと高尚なものというか。誰に言われたわけではないのに自分の衝動だけでやるので、自由だけど苦しい、というおもしろさはありますね。アート活動は続けたいですし、突然やりたくなる感じがあります。設計は生業ですね。設計とアート活動どちらもライフワークです。
――出口が違うだけというお話がありましたが、『古町100選』についてもお聞かせください。
アート・ストリート含め、その時に知り合った人で古町好きな人が周りにいて、まちのおもしろい部分を発見する活動をやったらおもしろいんじゃないか、となったのがロンドンから帰ってきて2年後の2017年9月です。最初のノリはそんなに大したことなく、当時トランプ大統領の選挙の時で、「Make America Great Again」というフレーズがあり、知り合いのアメリカ人が「Make Furumachi Great Again」とおもしろがって言っていたんですね。それがおもしろいから、Tシャツを作ってみんなで飲みに行こうというくらいのきっかけだったんです。実は「まちのちそう」で掃除機で吸って歩いている時にも着ていました。
その流れで、「空家等対策の推進に関する特別措置法」でどんどん空き家がなくなっていくのを受けて、看板を残していこうと看板の写真を撮って写真集を作ったりしていました。その他にも、まち歩きを普通にやってもおもしろくないということで、「カラフルマチ」というイベントを企画して、集まった人にくじ引きで色を引いてもらって、その色の写真を撮ってきてくださいと。そうすると普段気付かないお店とかが色をきっかけに目に入ってくるんですよ。こんなところに黄色い看板のお店がある、みたいな。それで最後には、持ち寄った写真を見せ合って紹介し合って。それを色ごとに並べると虹色になるので、古町ってこんなにカラフルだね、カラフルマチだね、と落とす。あとは、毎年「夕涼みピクニック」をやっていたりしました。
そんな活動をしている中で出てきた企画が「古町100選」です。最初はチーム(古町セッション)内で100選を選んでいたのですが、知っている所ばっかりで全然おもしろくなくて。このタイミングで、新潟市中央区の「新潟市古町地区魅力創造支援補助金」を使って何かできそう、100選をもうちょっとおもしろくできそうと思いました。そして、補助金も採択されて企画したのが、企画展「古町百選展」です。この時に、いろんな人に普段行くおもしろいお店を紹介してもらい、50人くらいに執筆を頼んで書いてもらって、それを写真に撮って展示しました。これが2023年2月です。上古町のSANやブルーカフェで1ヶ月間展示をしていたのですが、それをおもしろがってくれて、新潟駅南のMOYORe:で準常設展として1年くらいたまに展示してくれたりしました。
展示をしているときに、カフェなどではお客さんがいる時は見えないから本にしてほしい、という声が結構寄せられました。また、SANの副館長の金澤さんからも、もっといろんな人に見てもらった方がいい、県外の人にも見てもらえるようにした方がいい、編集手伝うので、と言ってくれたので、じゃあやるか、と。クラウドファンディングでお金を集めたのですが、最初に値段感を決めていたので、これくらいの値段に抑えるには全額ではないにせよクラウドファンディングでこれくらい資金を集めないと出せないな、という感じで集めたところ結果212%。これでようやく出版が決まりました。
――企画展から本を出版されるまでの活動を通して、やる前とやった後で、近藤さんご自身の中で変わったことはありましたか。
一番大きいのは、いろんな人に関わってもらったことで、それぞれが持っているおもしろい古町像を集められたことです。古町セッションのチーム内だけでやるよりも、オープンにいろんな人に書いてもらうおもしろさ。自分の知らないお店もあったし、それはすごく大きな違いです。また、おかげさまで反響がすごくあって、県外の人でこの本をきっかけに新潟に来てくれた人もいるんですよ。この本に載っているatoriさんに来たお客さんの中には、Amazonでこの本を買って横浜から来ました、という方も。そんなこと起こるんだ、と。まさに狙った通りのことですよね。
おそらく、古町好きの人が一番おもしろいと思うのですが、古町のおもしろさを県外の人に教えるツールとしてすごく役に立つので、自分のまちおもしろいから来てよ、とプレゼントしたり、英語翻訳付きなので海外にも送れたりします。

――「カラフルマチ」や『古町100選』など、さまざまな取り組みでまちと関わられてきたことを伺いました。最後のお話に出てきた、atoriさん。初めにキーワードになると仰っていました。ここからは、今回の会場「文化座本町Sono」のお話について伺います。この建物との出会いから伺えますか。
『古町100選』にも載っているatoriさんの設計をする話があった時に、お店の場所から一緒に探していたんです。お弁当だし、食文化に関係ある場所がいいなと思っていました。この「文化座本町Sono」があるフレッシュ本町のあたりは、かつて北前船で運んできたものや、信濃川から運んできた農作物や海でとれた魚を小舟に積み替えて売っていたエリアです。そういう食文化につながりがある場所がいいなと思っていました。そこで、フレッシュ本町で五徳屋十兵衛というカフェを構える宮原さんに、何かおもしろい物件ないですかと相談しに行ったんですよ。そうしたら、あそこに空き家になっているところがあるよ、とこの場所を教えてもらい、その場で当時のオーナーの田邊さんに電話してくれたんですよ。住所を聞いてくれて、ここに連絡するといいよと渡してくれました。
その住所に宛ててお手紙を書いて連絡はとれたのですが、コロナ禍だったこともあり、田邊さんは県外のためなかなか新潟に来れないけれど、新潟に行けたタイミングで話ができたら、という感じでした。お弁当屋さんの方は場所探しに急いでいたので、別の場所を見つけて2022年の2月にお店を出しました。そのお店ができた後に田邊さんから、今度新潟に行くので家を見に行きませんかと連絡をいただき、2022年9月にはじめてお会いしました。
この建物は、奥に蔵があって、真ん中に母屋、そしてフレッシュ本町沿いに店舗があります。明治22年の書物にも載っているのですが、古くは瀬戸物商をされていました。2022年9月の時に初めて中を見せてもらったのですが、「すごい、こんな建物が残ってるんですね」というのが最初の印象です。今みなさんがいらっしゃるのは母屋の客間なのですが、ここは何も変えていない状態です。明治に建ったにしてはすごく状態がよくて、綺麗に使われていて柱も全然傾いてなかったのがすぐ分かったので、すごく丁寧に使ってらっしゃるな、という印象でした。130年以上経っている建物だったので、蔵の中にはすごく古い時代から残されているものが色々ありました。蔵は新潟地震の時に床が外れちゃったみたいで、一部床が落ちていました。
――今は近藤さんがオーナーになられていますが、元々のオーナーの田邊さんはこの場所にとても思い入れをお持ちだったのではないかと思います。田邊さんと近藤さんの間で交わされたお話など、お聞きできる範囲で教えていただけますか。
最初に田邊さんとお会いした時は、自分がこれから何かやろうとも思ってなくて、家の中を見せてほしいという単純な興味でお話を伺いに行きました。そうしたら、田邊さんから相談みたいな感じで、コロナ禍でなかなか集まれないけれどこの場所は親戚で夏に集まるくらいで、自分も元気がいつまで続くかわからないし、お子さん含め親戚一同県外に住んでいて管理も難しいし引き継ぎ手も今のところいない、地域のために使ってくれる方が現れたら譲りたい、といった相談を受けました。その時から、自分だったらどうしようかと考え始めました。もし資金的に用意できそうであれば、他の人が変な風にするよりも自分がちゃんとこの場所を活かして地域のために使えることを考えるので、いろいろ教えてください、という感じでお話していきました。田邊さんと自分は、文化的な古い町並みが好きという共通点があったり、すごく気が合ったという印象でした。
ただ、どういう使い方をするかはすごく気にされていたので、自分だったらこうしようといったスケッチを書きました。母屋のうち今みなさんがいらっしゃる客間をレンタルスペースとして地域の人が使えたり、奥は自分がオフィスとして使おうかなとか、表側の店舗部分は商店街に面しているのでショップとかカフェが使って、とイメージしていました。
この構想中に、元Noismダンサーの池ヶ谷奏さんが、近藤が何かやろうしていると聞きつけて連絡をくれました。そこで建物を一緒に見て、その時に池ヶ谷さんから自分のダンススタジオを持ちたいという話を聞き、蔵は大空間でいいのではないか、ということで田邊さんにもその話をして、この方が蔵をダンススタジオにします、と紹介しました。
そして表側の店舗部分は、漢方系の薬剤師の方が体に良い薬膳カフェをやることになっています。それも地域のことを考えて、お年寄りが多いエリアだから、この地域が健康になったらおもしろいなと思って薬剤師さんを探していたんですよ。その時にatoriの方から、五泉で薬局をされていて、みなとぴあで「となう」という音楽と食と健康、季節などをテーマにしたイベントも開催されている森山和也さんを紹介してもらいました。話をしてみたら、この人にやってもらったらおもしろいなと思いました。そこで、森山さんに、ここで薬膳カフェやってくださいよと聞いたら興味を持ってくれたので、田邊さんに、この方が表でカフェをする予定です、と紹介しました。
こんな感じで、田邊さんにはそれぞれ会ってもらって、徐々に、それならば、という感じで進みました。田邊さんは芸術にとても理解のある方なので、池ヶ谷さんを紹介した時はすごく喜んでくれました。薬剤師の森山さんを紹介した時も、薬剤師がカフェをやるということ自体をおもしろく思ってくれて。この人ならば、という信頼を得られるような方を連れてこれたので、そこがポイントだったのかなと思います。
――そして今は「文化座本町Sono」になりましたが、建物について教えてください。
この建物は「文化座本町Sono」という名前で、フレッシュ本町沿いの店舗部分を「Sono壱」として、1階がカフェになります。2階に関しては実は後から決まったのですが、たまたま紹介してもらったカナダ人の夫妻が、日本中を旅行して新潟をすごく気に入ったので新潟を外国の人に紹介したいということで、これから観光業を始めるにあたり2階のオフィスを使ってくれる予定です。今は、表側の店舗と母屋は離れていますがつなげる予定で、庭をとおしてつながっていく場所をイメージしています。
母屋部分の「Sono弐」は、今みなさんがいらっしゃる客間のレンタルスペースとコワーキングスペースを設け、2階は県外から来た人などが泊まれるスペースにして、泊まりながら1階のコワーキングスペースで働いてワーケーションができたりすることも考えています。この間、池ヶ谷さんのダンススタジオ(蔵の「Sono参」部分)オープニング公演の時は、出演者がこの客間に泊まって、レジデンスみたいに使っていました。
蔵の「Sono参」は、1階がダンススタジオで、2階がピラティススタジオになります。
――「Sono参」の蔵部分は、先々週、10月12・13日にオープニングイベントでダンスの公演がありました。先程お話があった滞在クリエーションや、ダンス経験問わずに募集したダンサーとまち歩きをして作った作品などが上演され(Studio 奏蔵舎 オープンイベント トリプルビル ダンス公演)、様子を拝見していて、まちと一緒に作っていく印象を受けました。
――「文化座本町Sono」の構想がどこから出てきたのかと、名前の由来を教えてください。
東京の谷中にある東京藝大生が下宿していた巨大なアパート「萩荘」が立て壊される時に、最後だから好きにしていいよということで「萩荘」だから「ハギエンナーレ」という名前のアートフェスみたいなものがありました。それにすごい人数が来て、おもしろいから残そうよ、という流れになったのですが、それに行ってみておもしろかったこと。あとは、大阪の「空堀商店街」という所に「れん」というお屋敷の中にいろんなお店が入ってる場所があります。1つの建物の中に壁などで仕切られずに緩やかにつながっていて、歩きながら行けるみたいなのがおもしろいなと思っていて、それが「文化座本町Sono」の構想とすごくつながっていますね。庭がたくさんあって、建物は別れているけれど窓を開けてつなげたら、母屋と表沿いの店舗と一緒に使えるな、とか。ベースになってるのはそこですね。
名前の由来は、「Sono」は「庭」という意味で、新宿御苑の「苑」を訓読みして「その」です。庭でつながる文化施設、という意味もあるし、文化人が集まる場所という意味もあります。『装苑』という雑誌がありますよね。ファッションの装いの「装」と「苑」をくっつけて、ファッション業界の人が集まる場所みたいな意味になっていて、「苑」自体にそういう意味があります。なので、「庭」と「文化的な人が集まる場所」という意味をくっつけて、「Sono」という名前にしました。
――構想の元となる事例をご存じで、それを新潟に落とし込んでいく、文化的な人が集まる場所という要素を加えていく時に、元々の建物を再構築するようなことがあると思いますが、その時に気を付けたことや、不安だった要素や工夫した点などを教えてください。
まず、この客間は絶対に残してほしいという田邊さんの願いは最初から聞いていましたし、自分も何も変える必要はない、むしろこここそがこの建物のアイデンティティだと思っていました。客間は一番古い場所でもあるので、最初から客間を中心に考えました。
あとは、自分は「世代交代」だと思ってるんですけれど、英語でリジェネレーションと言うのですが、リノベーションではない。単純に、改築して新しい価値観を埋め込みました、みたいな感じではなくて、ニュアンスの違いでしかないのですが、この建物が文化的な使い方も含めて地域にちゃんと使われる状態でこのまま活かせる部分を残せるか、まちの人にどのようにオープンになるか、みたいなことをすごく意識して考えていました。
田邊さんにすごく感謝していることなのですが、所有権移転、引き継ぎのタイミングで田邊さんが、「今度近藤さんという方が引っ越してくるからよろしくね」と地域のいろんな人に自分が知らない間に話していてくれて、自分が挨拶に行ったら「ああ、あなたが」みたいな雰囲気になっていて。それが地域に入りやすくてありがたかったなと。また、はじめにこの建物を教えてくれた五徳屋十兵衛の宮原さんにもいろいろ相談させてもらって、「今度こっちに来ようと思うんですけど、どう思いますか」と。それで宮原さんから反対されたらやめようと思っていました。地域に入れないとやる意味ないなと思っていたので。そうしたら、宮原さんが「いいよ、いいよ」と言ってくれて。
最初から巻き込まれやすかったというか、地域に入りやすかった感じがすごくありましたね。それは田邊さんのおかげだし、宮原さんのおかげだと思っています。
――新しい人が起爆剤になるというか、新しい人に地域の人が巻き込まれる、という流れがイベントなどでは生まれるのかなと思いますが、近藤さんのような方、越してきた方が巻き込まれる状態というは、続いていくことや元々あったものを大事にすることを考えると、すごくいい入り方だったのかもしれませんね。
こんなにすんなりと入れるのは何でだろうなって思うと、やっぱり港町って外から来た人を歓迎するおもてなしみたいなものが、どこか根底にあるのかなと思います。全然排他的じゃない。周りの人に話をしても、「いいよ、一緒にやろうよ」とか「いいよ、来なよ」という感じなので、文化的・歴史的な背景がそこにあるからなのだなと勝手に解釈しています。
この地域での活動のひとつとして、デザイン業もやっていたので、下本町商店街の人から「チラシ作ってよ」と言われて作ったこともありました。 自分を商店街の人に知ってもらうきっかけになるかなと思って取り組みました。
また、自分がメインで関わっている「しもまち湊ボーダー」という取り組みもあります。これは、中央区地域課の方と一緒にやっている取り組みで、「ハマベリング!!!」で日和山浜をきれいにしたりイベントで外から人は来たりするけれど、地域とのつながりがあまりない状態だから地域の人ともうちょっとつなげたいね、ということで去年から、下町で活躍してる方やすでに地域で色々されてる方を呼んで、 どんなことしたらいいかというワークショップ(「ハマベリングネットワーク」)をやっています。自分は去年、餅つきと餅配りをフレッシュ本町沿いの空き店舗の部分でやり、その時に地域の人に下町のいい所や好きな所を聞くインタビューをしました。その取り組みについて、地域課の人から、それはおもしろいから続けてやってほしい、ということで、じゃあ一緒にやりましょうかと生まれたのが「しもまち湊ボーダー」です。
港町だけれどみんな海や川などあんまり普段感じてないから、海も川もある下町いいよね、っていうことを再確認するために、マリンファッションといえばボーダーだろうということで、みんなでボーダーの服を着て1日過ごしましょうというイベントです。商店街の店主のみなさんにボーダーの服を着てもらって、お客さんがボーダーの服を着て来たらちょっと話しかけて会話してくださいと頼んでいます。そうすると、普段でも商店街の中では井戸端会議をしているような雰囲気があるので、よりその日はみんな喋ってあったかい雰囲気になるかなと思ったのがこの企画です。下町の外から来た人は、やたら今日下町はボーダー着ている人がたくさんいるな、何やっているんだろうみたいな感じの、内から盛り上がって外の人が興味を持って来る、みたいな流れがいいかなと思っています。誰でも参加できる、1枚くらいボーダーの服を持っていたらいいなということで企画しました。
――餅つきのお話やボーダーの企画、すごく緩やかな入り込みというか、無理がなさそうだな、と感じました。
すでにそれぞれ活動がある中で、無理やり地域で一体になって一緒になりましょうって難しいじゃないですか。だから、どれだけハードルを低くするかみたいなことはテーマにしていたんですよ。最初は挨拶運動をしようとしてたんです。会話がたくさんあるのが下町のいいところだから、積極的に話しかける、という。けれど、挨拶運動しましょうと言っても、きっかけがないと誰も話しかけないし、もっと別の切り口で話すきっかけになったらいいなっていうのが、このボーダーの企画です。ボーダーを着ているということはイベント参加してるから話しかけていいよね、みたいな。でも、きっと知らずに着ている人もいると思うので、巻き込まれる人もいるでしょうね。よくある「ジャック」ですよね。
――いつのまにか巻き込まれている、その一部になっているという感じですね。
――今回テーマを、あるものに気づいて、新しい交流の場所、点を作るということに設定してお話伺ってきました。大学からロンドン時代のお話、そして「しもまち湊ボーダー」のお話から、近藤さんのまちに対する見方や関わり方を垣間見させていただきました。外からのアーティスト滞在も受け入れられたお話もありましたが、「文化座本町Sono」のオーナーとしての目線、これからここをどうしていこうか、といった夢を最後にお聞かせください。
外から人を呼ぶことは結構意識していて、健全な循環だと思っています。おもしろい人が集まってくる町がおもしろいと思っているので。そういう場所だからそれを作るという考え方と、この点があると周りが良くなるという考え方があると思います。私は、まずは場所を作ることがスタート、先にその点を作らないことには、拠点がないことには起こりえないことがあると思っています。言葉で表すと文化的な拠点ということになりますが、例えば コワーキングスペースも、そういった働く場所がないから人がなかなかこの地域に来ないだけだと思ってるので、もしそういう場所があれば、じゃあ引っ越してこようかな といった流れが生まれるし、そういう人が集まっている場所があれば展示する場所もあるしアート活動をこの地域でやってみようかな、となるかなと思っています。この場所から劇的に一瞬で何かが変わるっていうよりも、長期的に徐々にそういういい変化を生み出す場所として機能していったらいいなと思ってます。
もうすでにいい変化は生まれてきていて、近くにシェアハウスを作ってくれる人が出てきました。4軒が並んでいる所にお風呂が1つしかない空き家の物件なのですが、ぶち抜いて繋いだら10人くらい住めそうだから、シェアハウスにしたらおもしろいですよねと、その空き家のオーナーさんと話していたことから進んでいるものです。この話に興味があると言ってくれた人を引き込んできて、今もう工事が始まっています。そうやって、この場所があるから、といったつながりや兄弟みたいなものを増やしていって、徐々にいい変化が生まれるといいなと思っています。
①お話を伺ってると根底に敬愛の精神が流れていて、すごく様々なことがスムーズに行ってるような印象を受けました。とはいえ、これだけたくさんのプロジェクトをやられるには、反対意見やハードル、課題があるんだろうなと想像します。批判みたいなことが起こってきた時にどのように向き合ったり考えたりしてらっしゃいますか。
むしろ逆で、ある時から褒められ始めたんですよ。日本の学部の時はプロジェクトがうまくまとまりきらずに評価されなかったりしていましたが、イギリス留学以降のプロジェクトからあまり批判されなくなってきて。だんだん自分のストーリー立てが上手くなってきて、プロジェクトとしてちゃんと紹介できるようになってくると褒められて評価されるようになり、逆に批判されたいという謎の精神が生まれてきました。批判がないものは逆に価値がない、賛否両論で議論が生まれるものこそ本当に価値があると思っているので、今、批判されなくなってきていることにすごくもどかしさを感じています。
この場所に関しては、地域の人も興味を持っているんですよね。こんな場所があったんだ、そもそも知らなかった、という。知らなかった所に入れるようになってちょっと嬉しい、 みたいな感じなのでしょうかね。この場所で新しいことをやることに対しての批判は全然ないですね。
――批判を乗り越えて、みたいなことが一昔前のアクセスストーリーのように勝手に思っていたのですが、そうではない流れができているんだなと思いました。
うまくいかないことも当然あって、だいぶいろんな人に迷惑をかけていると思います。そういうのは確かにあるけれど、乗り越えているというよりも、どう次に活かすか、という感じですね。
――たくさんの人が集まってくると、価値観の違いが生まれたり、すれ違いとか意図しなかったところで相手に裏切りだと思われたりして人が離れていくみたいなことが起こりうるんじゃないかと勝手に想像するのですが、そういう痛みはありますか。
自分は一匹狼タイプ、来るもの拒まずというタイプで。その根底にあるのは、「コミュニティは永続しない」というのが常にあります。古町セッションに関しても、コミュニティではなくて企画団体なのです。今度こういうのをやるけど来る人来ていいよ、という感じです。基本は英語インストラクターの方と2人で企画していて、ただ循環している感じですね。
「コミュニティは永続しない」という言葉は、はてなブログを作った近藤淳也さんの言葉です。離れていく人を無理に引き止めても、いいことないですよね。適度な距離でいいと思っています。
②この建物との出会いのきっかけから、どのように活用していくかというお話を伺いました。自分で買って活用するという大きな決断を一番後押しした思いはどういう気持ちだったのでしょうか。自分はプロジェクトのマネジメントをして実働は誰かにやってもらうというやり方や、物自体を引き受けるのは別の方で、というやり方もあると思います。
むしろ、自分でできないならやらないですね。それができるから引き受けたというか、自分がこういう場所になったらいいなっていうイメージを実現できそうだなっていう感覚がどこかにあるから引き受けるし、引き受けるからにはちゃんと一緒にやる人を運命共同体として引き込んでくる。自分がこういうことをやりたくて探していたわけではなく、この場所が先にあるという、結構運命的な建物との出会いだったわけですよね。こういう場所があったらいいな、「萩荘」みたいなものが新潟にあったらおもしろいなって思っていて、いつかやりたいと思っていたけれどきっかけがなくて、そしてこの場所に出会った、という感じですね。投資だと思っていますが、まさかとてつもない借金を抱えてやるとは自分も想像していなかったですね。
③今回まとめてお聞きしたので、トントン拍子に全てがうまく行っているように聞こえるのですが、ものすごく困っていることはないのでしょうか。一人でもやるぞという意思や、離れていく人は止めないという相手にとっての緩やかさが、近藤さんを受け入れる空気につながっているのだと思いました。新潟の今までのまちづくりはコミュニティ主義というか、まずはコミュニティをつくる、良くも悪くも核の人がいてそこに群れていってしまう。それに対して新しい形で展開されている印象でした。
困っていることというか自分の課題は、自分でやりすぎちゃうことです。やりたがりなので、写真も撮る、映像も撮る、ウェブサイトも作るみたいな感じで全部自己完結してしまいがちで、よくないっていうのはわかっているけれどなかなかできてなくて。最近は、「しもまち湊ボーダー」の企画はちゃんと予算をつけてもらったこともあり、自分でどれだけやらないか、企画に徹しないといけないなと思い、少しずつ自分がやらなくてもちゃんとうまくいくように意識しています。
それができたのは、「古町100選」が大きいかもしれません。企画のためにチームを作り、自分がいいなと思う人に声をかけて、企画自体をおもしろいと思ってくれている人、仕事というよりも企画として関わりたいと思ってくれる人にやってもらえたので、そういうメンバー作りができることが一番うまくいくんだなということがちゃんとわかった感じですね。自分でやりすぎちゃうという課題があったから、それを一歩でも解決するためにチーム作りが全てというやり方をあえてしています。
――これまでのお話で出てきた、企画ベースの人集めということとすごく今つながったなと感じました。
DAO(分散型自律組織)的ですよね。要は、(従来型の)組織じゃない。それぞれのエキスパートがちゃんと動いていて、外から見ると全体としてうまく回ってるように見える。それが今の働き方に近いというか、フリーランスの人がプロジェクトごとに集まって、プロジェクトが終わったら解散して。それが健全な循環だと思います。引き止めない方がうまくいく気がします。
――執着しないということでしょうか。
そうですね。執着しない。選択肢を無限に持っておいて、これがダメならこれで、というようにやっていくという感じですね。
④近藤さんは、普段から気になる建物を見つけたりするのが上手なのかな、古い建物に対して気にしながらまちを歩いているのかな、建物に対してアンテナが反応される方なのかなと思いました。今日のお話から、いろんなご縁がある方だなと思ったのですが、人に対してもピンとくる人がいらっしゃるのでしょうか。
対まちに対してすごくアンテナを張っていると思います。自分だけが見られる秘密の地図があって、この蔵いいな、とかいっぱいピンを立てていますね。人に関してはどうでしょう…。3~4か月に1度くらいのペースで京都に行き、ワーケーションをしているのですが、そこでの、おもしろいことをやってる人がおもしろい人を連れてきて紹介して、そこから広がっていくというフリーランスのコミュニティがおもしろいのかもしれないです。経営者とはまた違う、能力だけで勝負してる人のつながりは積極的に取りに行ってるのかもしれないですね。自分から取りに行ったのが自然につながっている感じがあります。周りが自分のことを理解してくれていて、近藤はこういうことをおもしろそうときっと思うに違いない、と紹介してくれたりするので、それはすごくありがたいですね。自分が人を選んでいるというよりも、周りが人を選んでいると思っています。